震災から学ぶ「準備をして用意できること」
阪神・淡路大震災から30年・阪神ブロック協議会公開講座
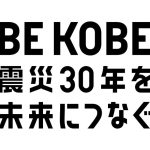
日本代協阪神ブロック協議会(先小山剛ブロック長・兵庫県代協会長)は、2月12 日(水)14 時から、神戸市中央区の神戸市産業振興センターのレセプションルームで公開講座「阪神・淡路大震災から30 年。震災から学ぶ。準備をして用意できること。」を開催しました。
第1部では特定非営利活動法人日本防災士会全国講師の横山恭子氏が「『そなえ~SONAE~』を合言葉に」を、第2部では兵庫県危機管理部総務課副課長兼総務班長の津田徹氏が「阪神・淡路大震災からの兵庫県の歩みと防災対策について」をテーマにセミナーが行われました。
開催にあたり先小山ブロック長が挨拶に立ち、「今年1月17日、阪神・淡路大震災から30年が経過しました。今回の公開講座が、いつ起こるか分からない自然災害に対して常日頃から備えておくべきことを再確認していただける機会になればと思います。我われ代理店の活動の中にBCP策定や事業継続力強化認定の申請などがあります。代理店自身はもとより、これをお客様にいかに伝えていくかが重要です。そういった意味で、我われの行動も再確認していただきたい」と述べました。
防災士 横山 恭子(たかこ)氏のセミナー

続いて、横山氏が第1部セミナーを行いました。同氏自身、阪神・淡路大震災で被災され、ボランティア活動に参加した際に防災活動について思うところがありました。2006年に結成された加古川市の消防団女性分団の初代代表に就任し、防災活動をしながら防災に関する知識や技術を修得するために2011年に防災士資格を取得。その後、東日本大震災、熊本地震、能登半島地震など各地でチェーンソー、重機等を取扱うテクニカル・ボランティアとして支援活動を行っています。セミナーの冒頭、同氏は、昨今は自然災害に限らず、インフルエンザやコロナといった感染症など今までになかった災害が発生している現状を述べるとともに、災害は時と場所を選ばないと警告。聴講者に地震が発生した場合にどういった行動をとるかを会場で避難訓練させたうえで、机の下に潜り込むという誰もが行う決まりきった避難行動は古い考え方で、地震時には「頭と首を守る行動をとるために思考を働かせる」よう、想像力と対応力をもって行動することだと強調しました。そして、信号が赤の時は停止することが当たり前のように、防災に関しても非難訓練の時だけではなく、年齢の小さい時期から、日々の生活の中で当然のように取り組むことだと述べました。

災害に対する備えは大きく、次の3つに分かれるといいます。
①物の備え(非常食や備蓄品、家具の固定など)
②お金に関する備え(現金、保険、制度など)
③心のための備え(自分の心を安心させる)
①の「物の備え」では、食より先に排泄が問題になるとし、不特定多数で使うトイレより家族で使うトイレを準備し、トイレットペーパーやティッシュ、ごみ袋、夜間に使用する際のライトをセットで用意すること。また、災害時には気力と健康を保つために自分(家族)が食べたいもの、アレルギー等を考慮した食べることができるものを備えること。そして、ケガなく非難するために家具を固定しておくことだと述べました。
②の「お金に関する備え」では、現金はもちろん、保険は環境の変化とともに見直すこと、そして万一被災した場合に受けられる災害弔慰金、災害障害見舞金などの制度を知っておくことだとしました。
③の「心のための備え」では、災害時の不安を軽減させる備えとして情報を得ることができる各種の災害・防災アプリを設定するとともに、家族間で連絡先、集合場所、また外出の際には誰とどこに行くかなどを共有しておくことが重要だと述べました。また、日ごろからコミュニケーション豊かなまちづくりをしておくことも心の備えになるとし、最後に「今日から、そなえ会話をはじめましょう」と締めくくりました。
兵庫県危機管理部防災支援課によるセミナー
第2部では、津田氏が、阪神・淡路大震災から得た教訓として、下記のそれぞれに兵庫県として取り組んでいる対策を紹介しました。

①災害に対する備え
②初動対応
③地域防災力
④防災関係機関相互の連携
⑤災害に強いまちづくり
近い将来に予想されている南海トラフ地震の県内被災想定では、南あわじ市では震度7、最高津波推移8・1mとなり、兵庫県全体では死者数が最大約2・9万人と予想されています。しかしながら、避難体制の確保、避難訓練、避難行動支援者対策など避難対策を徹底すれば死者数を400名まで減少させることができるのではないかと述べました。そして、その実現に向けて地域防災の向上を図るために、
①防災意識の向上・維持・普及
②個人、地域における自助・共助の強化
③事業者としてのレジリエンスの強化
④事業者としての共助
が重要なポイントになると話しました。
第3部では、兵庫県危機管理部防災支援課副課長の西岡武則氏が同県独自の自然災害に対する共済制度であるフェニックス共済について解説しました。
閉会挨拶
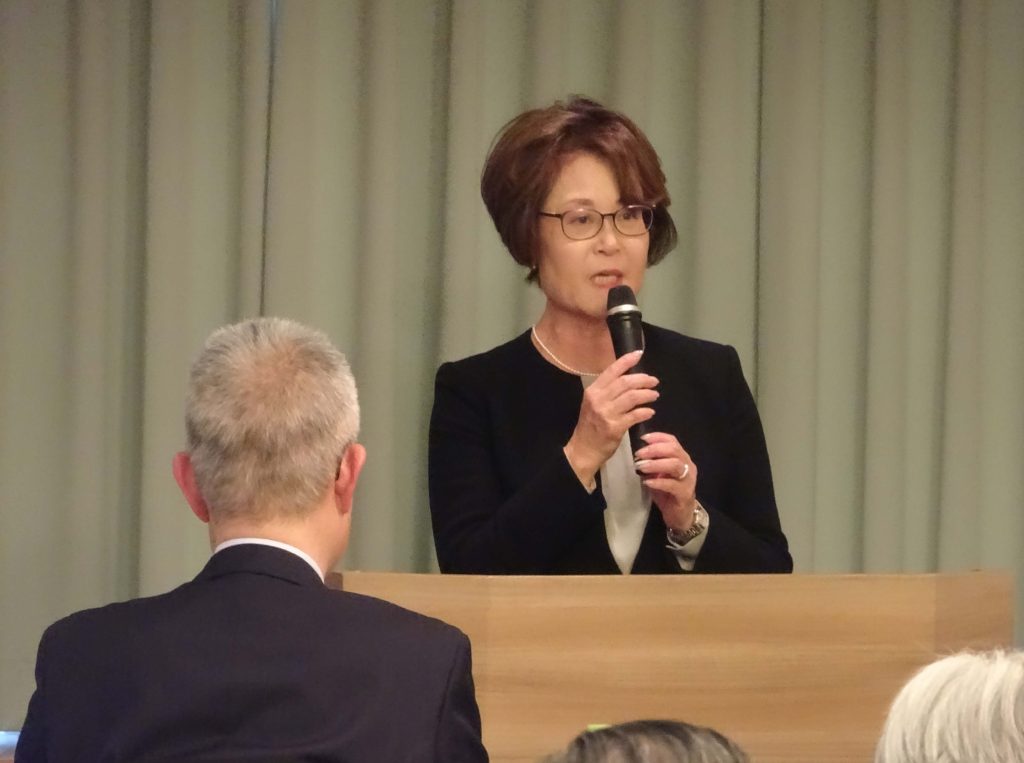
最後に大阪代協の新谷香代子会長が「本日、阪神・淡路大震災から30年という節目でこのような公開講座が開催されたことも何かの巡り会わせだと感じます。わが国は地震大国であり、今年も震度5以上が5回発生しました。横山先生がお話しされたように、私たち業界はお金の備えで力になれます。この30年の節目に今一度心にとめて被災された方の再建に力強く、少しでも力になれるよう努めてたいと思います。これからも皆さんと力を合わせ防災、減災に向かってまいりましょう」と挨拶し、閉会となりました。

(記事:新日本保険新聞社)
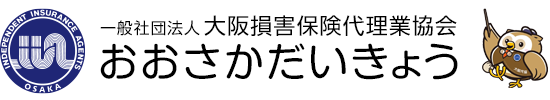

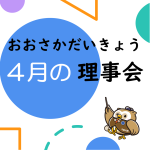
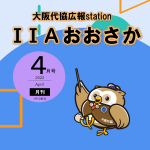
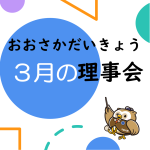
 ページの先頭へ
ページの先頭へ